Raspberry Pi 3、Pico、激安USBキャプチャボードで作るPiKVM – ソフトウェア編
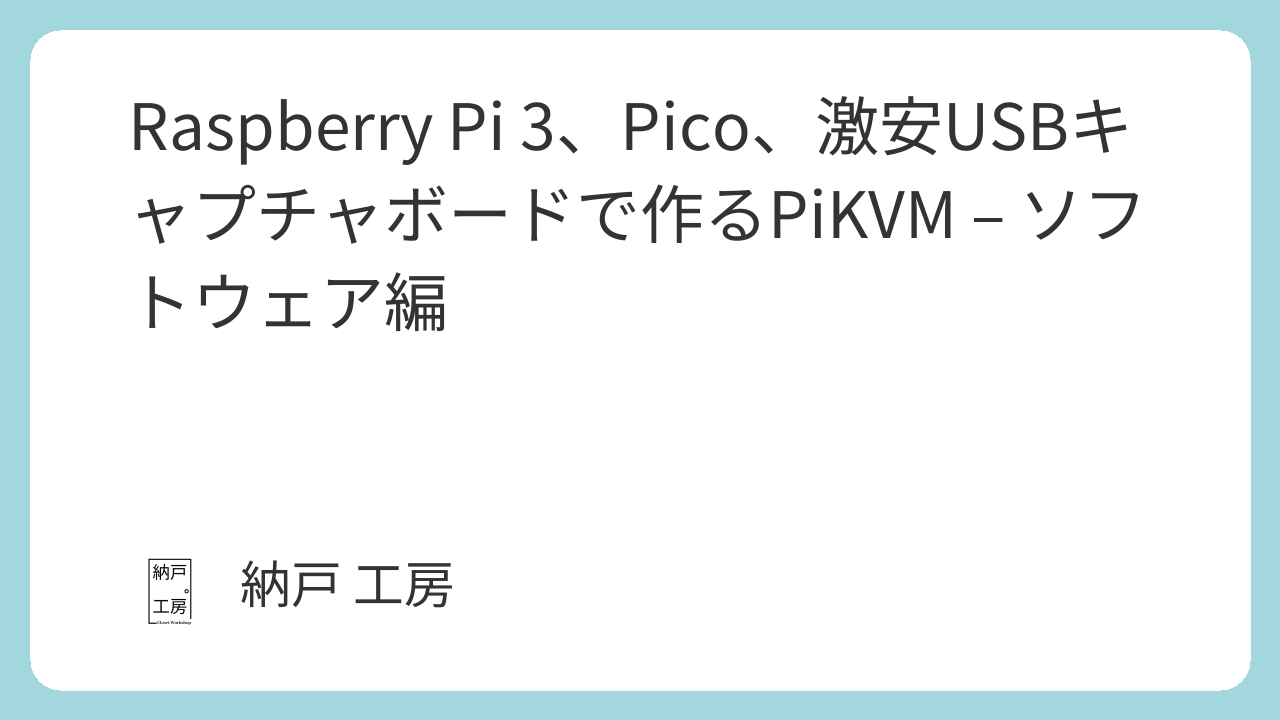
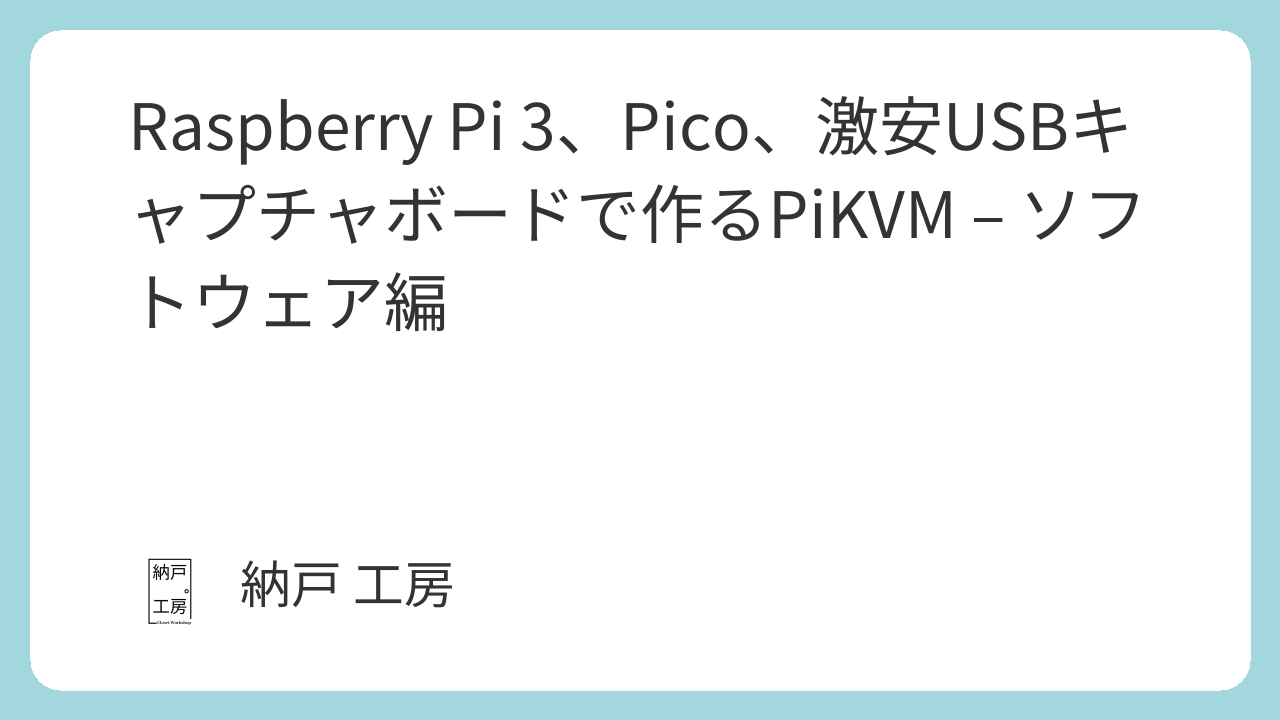
ハードウェアの組み立てが完了したら、次はソフトウェアのセットアップです。本記事では、Raspberry Pi Picoもどきへのpico HID書き込みと、Raspberry Pi Imagerを使用してPiKVM V1(HDMIUSB, RPi3用)のOSイメージを書き込む手順を中心に解説します。なお、今回の用途はASRock Beeboxのモニタリングであり、PS/2キーボードやマウス、ATXコントローラは使用しないシンプルな構成です。
Raspberry Pi Picoへのpico HID書き込み
pico HID書き込み手順
-
イメージのダウンロード
Pico用の書き込みイメージ「pico-hid.uf2」は、こちらのGitHubリリースページからダウンロード可能です。 -
書き込み手順
Pico本体のブートボタンを押した状態でUSB接続を行うと、USBドライブとして認識されます。
この状態で、ダウンロードした「pico-hid.uf2」をUSBドライブにコピーしてください。
※今回はPS/2キーボードやマウスは使わないため、これだけで書き込み完了となります。


PiKVM OSイメージの書き込み
OSイメージの選定と書き込み
-
書き込みツール
Raspberry Pi Imagerを使用して、PiKVM V1(HDMIUSB, RPi3用)のOSイメージを書き込みます。
※USBキャプチャボードを使用しない場合や、別のRaspberry Piバージョンを使う場合は、使用するイメージが異なるので注意してください。


-
イメージのダウンロード先
OSイメージはこちらの公式サイトからダウンロードできます。
ダウンロードに時間がかかるため、最初は自作ビルドを試みましたが、多数のエラーにより断念し、公式イメージのダウンロードをおとなしく待つことにしました。 - イメージのインストール
インストール後の初期設定
ブラウザでのアクセス
-
OSイメージの書き込みが完了し、PiKVMに起動後、ブラウザで対象のPiKVMにアクセスしてください。割り当たっているIPはRaspberry PiにHDMIをつなげて確認する必要あり?
-
デフォルトのログイン情報は:
ユーザーID: admin
パスワード: admin
画面表示がされない場合の対処法
もしPiKVMの画面がブラウザ上に表示されない場合は、以下の手順でコンソールから設定を変更してください。
-
コンソールにアクセス
rootユーザー(初期パスワード:root)でコンソールにログインします。 -
編集
ファイルシステムのRWモード切替
/etc/kvmd/override.yaml の編集
変更の適用
[root@pikvm ~]# rw [root@pikvm ~]# vim /etc/kvmd/override.yaml kvmd: streamer: forever: true cmd_append: [--slowdown] [root@pikvm ~]# ro [root@pikvm ~]# systemctl restart kvmd
これで、対象サーバの画面表示が可能になるはずです。
初期トラブルと学び
初期段階では、PicoとRaspberry Pi 3間の配線を誤って接続してしまい、SPI接続エラーが継続的に発生しました。正しい配線を再確認し、HIDのリセットをすることで問題は解決しましたが、ソフトウェアのセットアップ前にハードウェアの接続確認が非常に重要であると痛感しました。
まとめ
今回のソフトウェアセットアップでは、Raspberry Pi Picoもどきへのpico HID書き込みと、Raspberry Pi Imagerを用いたPiKVM V1 OSイメージの書き込み、さらに初期設定でのトラブルシュートを行いました。公式ドキュメント(PiKVM V1)やGitHubのリリース情報を参考に、手順通りに進めることで、ASRock Beeboxのモニタリング用途に対応したシンプルかつ安定したPiKVMシステムが完成しました。
ケース作成編に続く



